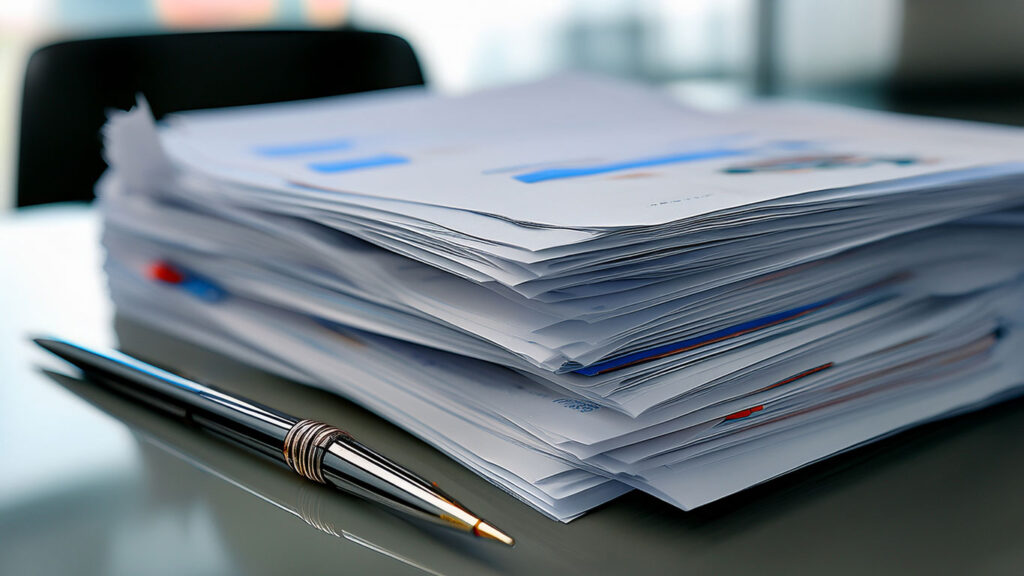
情報漏洩は外部からの攻撃だけでなく、日常業務の中からも発生します。特に社内文書の印刷や持ち出しは、気づかないうちに情報が社外へ流出する、大きなリスクです。紙に出力された情報が外部に出ると、追跡や削除ができず、その制御が極めて困難になります。
このような紙媒体を通じた情報漏洩に、最も効果的な対策が「印刷制限」と「透かし印刷」です。本記事ではその仕組みに加え、現実的で運用しやすいソリューションについても紹介します。
目次
印刷制限とは:紙への出力を制御する基本対策
印刷制限とは、ユーザーやファイル単位で印刷を禁止・許可する仕組みのことです。たとえば、社内での閲覧は認めても印刷は不可とする、あるいは上長の承認があった場合のみ印刷を許可するといった柔軟な運用が可能です。これにより、無断印刷や誤印刷による情報の持ち出しを防止できます。
実務においては、単に印刷を制御するだけでなく、アプリケーション単位で印刷を管理できることが理想的です。Word・Excel・PDFなど、主要なアプリケーションごとに印刷の可否を設定することで、業務に必要な範囲のみ印刷を許可できます。
さらに、印刷操作のログを自動的に取得し、後から追跡できる仕組みを備えれば、内部統制の強化にもつながります。業務を止めることなくセキュリティを高めること。その使いやすさこそ、印刷制限を運用するうえで最も重要なポイントです。
透かし印刷とは:印刷物に責任を明示する抑止策
透かし印刷とは、印刷時にユーザー名・日時・端末情報などを文書内に自動で埋め込む機能です。これにより、「誰が印刷したのか」を明確にでき、印刷物の持ち出しや不正コピーを効果的に抑止します。
透かし印刷の機能としては、透かしの文字の自由度が高く、社名やログインID、コンピューター名など任意の項目を組み合わせて表示できることが理想です。さらに、印刷時の解像度に合わせて透かしを最適化できれば、文字の可読性と美観を両立させることができます。
見た目を損なわずに責任を明示できる仕組みであれば、社内資料や営業資料など、実際の業務でも安心して活用できるでしょう。
印刷制限と透かし印刷を組み合わせた、情報漏洩対策
印刷制限と透かし印刷を組み合わせることで、リスクを防ぐだけでなく、「見える化」して管理することが可能になります。印刷を制御しつつ、許可された印刷物に透かし情報を付与すれば、追跡性と抑止効果を同時に高められます。
弊社のコプリガードでは、これらの制御設定を一元的にポリシー管理できるため、全社的なルールの統一が容易です。さらに、USBメモリーやクラウドストレージなど外部媒体へのコピー制限機能も提供しており、印刷とファイルコピーという主要な流出経路を多面的に封じ込めます。単独の機能に依存せず、複数の制御を組み合わせて運用できる点が、大きな強みといえるでしょう。
印刷制限と透かし印刷に適した、実務ソリューション
弊社のコプリガードは、印刷制限や透かし印刷に加え、外部媒体制御・ファイル持ち出し制限・画面キャプチャー防止・操作ログ管理など、多層的な情報保護を一体的に提供します。これにより、内部不正や誤操作、退職者による情報持ち出しなど、現場で起こりやすいリスクを包括的に防止します。
またポリシー変更や設定反映も一括管理できるため、システム管理者の負担を軽減し、中小企業から大企業まで、段階的な導入や拡張が可能です。「導入して終わり」ではなく、運用し続けられるセキュリティを実現できることが、最大の強みといえるでしょう。
まとめ
印刷制限と透かし印刷は、情報漏洩防止の基本であると同時に、社員一人ひとりのセキュリティ意識を高める教育的な効果も持ちます。特にコプリガードのように、印刷制御・透かし印刷・外部媒体対策を一体的に管理できる仕組みは、現場で実効性のある運用を実現します。
重要なのは、制限を「負担」と感じさせない運用設計です。社員が安心して働きながら、企業としての情報防御力を高められる環境を整えること。それこそが、持続的なセキュリティ文化を築く第一歩といえるでしょう。
以上、「印刷制限と透かし印刷で防ぐ情報漏洩」について、ご説明しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
<印刷制限と透かし印刷>による情報漏洩対策は
「コプリガード」!
●不正なファイルの持ち出しにつながる操作を制御!
●コピーによる持ち出しも同時に防げます!

※本記事の掲載事例は現時点での当社調べの内容です。
本記事の作成者:村澤
所属:株式会社ティエスエスリンク / 営業部

企業と個人のための「情報漏洩対策ソフト」:基礎から高度な選択まで
「情報漏洩対策ソフト」は、多様なニーズに対応しています。ファイルの持ち出し制限、USB管理、ファイル交換ソフトの制限など、基本的な機能から高度なセキュリティ要件まで、限られた予算内で、最適なソフトの選定方法と、導入の流れをこの記事で解説します。

